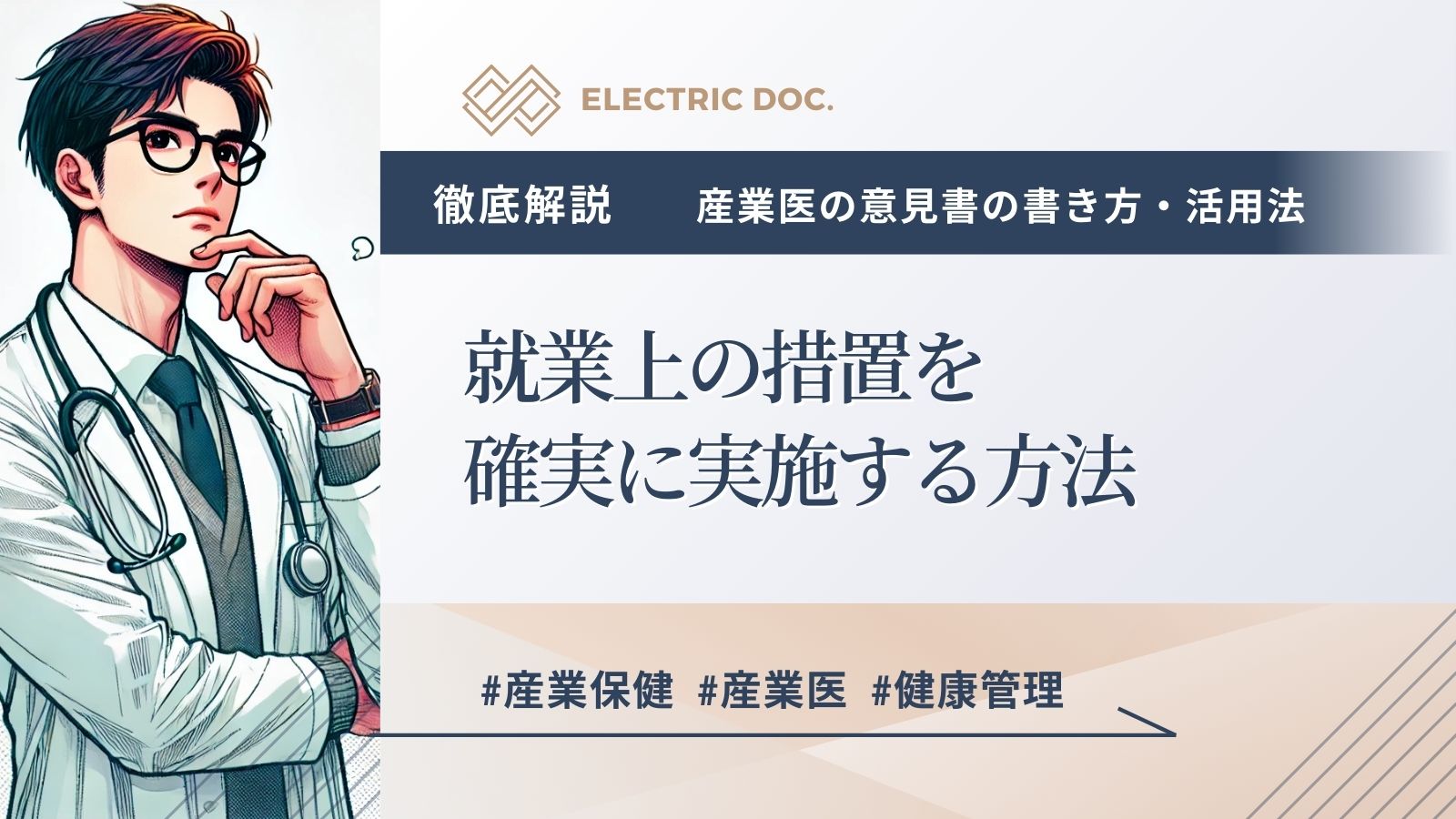
「意見書を出した後、実際に現場で実施されているのだろうか?」
「就業制限を提案したけれど、その後の職場での対応がどうなっているのか分からない……」
「必要がなくなったはずの措置が、そのまま続いているのではないか……?」
産業医として意見書を作成した後、その内容がどのように実施されているかを確認することは重要です。意見書が現場で適切に活用されなければ、従業員の健康を守ることにはつながりません。また、必要がなくなった措置が見直されずに続いていることもあります。
例えば、業務負担を軽減するために設定した短時間勤務が、従業員の体調が回復してもそのまま続いている場合、職場の人員配置に影響を与えたり、本人のキャリアに悪影響を及ぼすことがあります。適切なタイミングで見直しを行わなければ、意見書の目的が果たせず、形骸化してしまいます。
意見書が形だけのものにならないためには、発行後の措置状況を把握し、必要な措置が適切に実施され、不要な措置は解除されるようにすることが不可欠です。本記事では、意見書の実効性を高めるための確認方法と、不要になった措置の見直し方法について解説します。
就業制限が「かけっぱなし」になっていませんか? 定期的な見直しを忘れずに!
現状と課題:措置が適切に実施されない理由
産業医が意見書を発行しても、その内容が適切に実施されず、形骸化してしまうことがあります。また、一度実施された措置が見直されずに続いている場合もあります。これにより、健康管理上のリスクが放置され、職場の運営にも影響を及ぼすことがあります。こうした問題の背景には、いくつかの根本的な課題があります。
① 業務の都合で就業制限が守られない
意見書の内容を企業が理解していても、職場の状況によって就業制限や配慮事項が守られないことがあります。特に、人手不足や繁忙期の業務負担増加により、就業制限が守れないことがよくあります。
例えば、「残業を制限する」と決めたにもかかわらず、業務量が調整されないままでは、長時間労働が続いてしまうことがあります。また、業務の特性上、トラブル対応や顧客対応を避けられず、就業制限が守られないこともあります。
② 従業員が就業制限を守らない
意見書に基づく就業制限が設定されていても、従業員が「もう大丈夫だ」と自己判断し、制限を破ることがあります。
特に、持病を抱える従業員の場合、症状が一時的に良くなると「普通に働ける」と考え、無理をしてしまうことがあります。例えば、「長時間労働を避けるように」との指示が出ていても、周囲に遠慮して業務を引き受け、結果的に過労を招くことがあります。また、「もう治った」と自己判断して、就業制限を無視することもあります。
③ 上司が部下の業務の状況を把握できていない
就業制限が適切に運用されるためには、管理職がその内容を正しく理解し、適切に監督することが必要です。しかし、実際には、管理職が部下の業務状況を十分に把握できず、結果的に従業員が通常通り業務を続けてしまうことがあります。
特に、業務遂行に関する部下の裁量が大きい場合や、管理職と従業員の勤務場所が異なる場合、在宅勤務の場合なども、上司が部下の実際の業務状況を把握しにくいことがあります。
④ フォローアップや見直しが行われていない
意見書に基づく措置が適切に実施されていても、その後のフォローアップや見直しが行われず、不要な措置が続いてしまうことも問題です。
例えば、復職直後の負担軽減措置として設定された短時間勤務が、本人の健康状態が回復しても解除されず、そのまま続いてしまうことがあります。これにより、本人のキャリア形成や業務遂行能力に影響を与え、職場全体の人員配置にも支障をきたす可能性があります。また、「就業制限を解除するかどうか」が検討されないまま放置されると、他の従業員の業務負担が増加し、職場の公平性が損なわれることもあります。
解決策:就業制限の実施状況を把握し、適切な見直しを行う方法
意見書の措置が確実に実施され、不要な措置が放置されないようにするためには、次の2つの対策を実践することが重要です。
① 産業医が就業制限の実施状況を把握する
就業制限が適切に実施されているかを確認するために、産業医が定期的に状況を把握・確認することが不可欠です。
- 本人との定期面談を実施し、就業制限が守られているかを直接確認する。
- 人事担当者と定期的に情報を共有し、職場での対応状況を確認する。
- 必要に応じて、管理職と直接相談し、実施が難しい場合の代替措置を検討する。
フォローアップ面談の際には、本人に現在の就業制限の状況について確認してみることも大切です。
② 意見書に有効期限を設け、定期的な見直しを行う
意見書に有効期限を明記し、措置の継続・終了の判断基準を事前に決めておくことで、不要な措置が長期化することを防ぎます。有効期限が過ぎた後は「通常勤務可能」とするか、「産業医面談を実施して措置の内容を再検討する」のいずれかを記入します。また、就業制限を設けている社員の管理リストを作成し、産業医と人事担当者で共有しながらフォローアップに活用することで、より適切な管理が可能になります。産業医と人事担当者で定期的な協議の場を設け、それぞれの社員の対応状況や今後の計画について共有するようにしましょう。
- 意見書に「有効期限:○月末まで」と明記し、フォローアップの仕組みを作る。
- 有効期限が切れた後の対応として「通常勤務可能」とするか、「産業医面談を実施して継続・終了を判断する」のいずれかを記入する。
- 就業制限中の社員リストを人事担当者と共有し、定期的に確認を行うことで、措置の実施状況や見直しの必要性を把握する。
- 個人情報の管理に配慮し、リストの内容や取り扱いには十分な注意を払う。
まとめ:定期的なフォローアップと明確な有効期限の設定が不可欠
産業医の役割は、意見書を発行した後も引き続き関与し、提案した措置が正しく実施され、定期的に見直されるように働きかけることです。このような取り組みを行うことで、産業医の意見書が単なる形式的なものにならず、職場での健康管理が実際に効果を持つものとなるようにしましょう。




