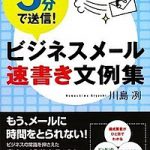企業の産業保健分野で専門職として働いていると、人事部や産業保健チームと連携・議論する場面が多くあります。その際、自分なりに根拠のある方法や他社で実績のある施策を提案しても、「現場の負担が大きい」「自社の風土に合わない」など、思うように受け入れてもらえず、もどかしさを感じることは珍しくありません。
「科学的根拠(エビデンス)のある、他社でも成果をあげている効果的な方法なのに、なぜか採用されない ……」
また、「なぜこの効果的な方法がうちでは採用されないのだろう」と悩んだ経験がある方も多いでしょう。しかし、どんなに科学的根拠のある内容でも、組織の意思決定には様々な事情や背景が影響するため、必ずしも自分の意見がそのまま通るとは限りません。
こうした場面で感じる戸惑いや無力感にどう向き合うかは、組織で健やかに働くうえで重要なテーマです。今回は、そのようなときに私自身が意識している「信頼を積み重ねるための3つの姿勢」についてお話ししたいと思います。
1. 自分の考えと異なる意見こそ、まず傾聴する
私たち専門職は、どうしても「医学的な正解」を優先したくなります。しかし、組織には組織の論理(予算、人員、タイミング、社内政治など)があります。たとえ自分の提案が退けられそうになっても、また、到底納得できそうにない決定だったとしても、まずは相手の意見に礼儀正しく耳を傾けましょう。
これには3つの大切な理由があります。
- 自分の話を相手に冷静に聞いてもらうため
「こちらの話を聞いてもらうためには、まず相手の話を聞くこと」。相手から見るとこちらの意見は「自分とは異なる意見」です。このお互いの関係がなければ、こちらの意見も、相手に聞いてもらえません。 - 背景を理解するため
「なぜその意見が出るのか?」という相手の背景を知れば、「自分と意見は違うが、その懸念も理解できる」という共通点が必ず見つかります。 - 今後の協力関係を維持するため
もしここで、相手を否定したり批判的な態度をとったりすると、「気難しい人」「協力しづらい人」というレッテルを貼られてしまいます。そうなると、将来、別の仕事で協力が必要になった時に困るのは自分自身です。
相手と意見が異なる場面では、まずは不必要な対立構図になることを避け、良い関係を維持することを優先するのがおすすめです。自分と相手の意見が違うからといって、相手の人格や知性、常識、職業倫理までを疑ってかかる必要はないのです。
自分の考えをいったん脇に置いておき(何か言いたくなる気持ちをおさえて)、相手の話に耳を傾けましょう。そのときの聞き方としては、産業医や産業看護職の方であれば「社員と面談する時と同じ気持ちで話を聴く」というと、イメージしやすいかもしれません。
また、相手の意見に耳を傾けることで、自分の考えとも相手の考えとも少し違う、「お互いに納得しやすい第3の解決方法」が見つかることがあります。話を丁寧に聴く姿勢があると、こうした新しい選択肢を思いつきやすくなります。
2. 自分のアイデアに「固執」しすぎない
組織で物事を決めるときは、「自分の案を通すこと」よりも「より良い判断ができるよう、意思決定のプロセスを支援すること」を意識しましょう。具体的には、会議がスムーズに進むように情報や論点を整理したり、メンバーが考えやすい環境を整えたりする役割を大切にします。
会議では、チームのメンバーや責任者が納得した上で結論を出せるように、いくつかの選択肢を示すことが大切です。たとえ、自分の案が最良だと思っていても、無理に誘導するような進め方は避けましょう。また、最初から採用するつもりのない案を混ぜて、自分の意見に寄せるようなやり方も控えましょう。
議論の場では、専門家として、どの案に対しても平等に、冷静に判断材料を示す役割を担います。医学的な視点だけでなく、「現場への負担」「コスト」「納期」「実行のしやすさ」「タイミング」「関係者への配慮」など、組織として考えるべき点も含めて整理することが重要です。
自分の意見にこだわりすぎると、協力してくれるはずの相手との距離ができてしまいます。いったん自分の意見を忘れて、「どの案に決まってもかまわない」というくらいの軽やかさを持つことが大切です。そして、最終的な決定はチームや責任者に任せましょう。
このように「自分の意見が通ったら勝ち・通らなければ負け」という勝ち負けの感覚を手放すことは、スムーズな合意形成を助けるだけでなく、自分自身の精神的なストレスを減らすことにもつながります。
3. 決まったことは、プロとして完璧に実行する
最後に、ここが最も重要なポイントです。議論の結果、もし自分自身の考えとは違う案が採用されたとします。その時、不満を述べるのではなく、「決まったことはきっちりと実行する」のがプロとしての姿勢です。
「自分の意見とは違うけど、チームで決めたことだから、きちんと成功させよう」と気持ちを切り替え、粛々と実行に移す姿勢こそが、「この人は中立的で、信頼できる人物だ」という周囲からの評価につながります。
まとめ:その「信頼」が次の提案を通す力になる
自分の意見が通らなかったとしても、それは決して「負け」ではありません。今回、周囲の意見を尊重して合意形成に協力し、決まったことをプロらしくきちんと実行した事実は、必ず「周囲からの評価や信頼」へとつながります。
その信頼があれば、次にまた重要な提案をする際に、周囲は以前よりも真剣に耳を傾けてくれるはずです。また、今回は意見が違った同僚も、別の場面では強力な味方になってくれるかもしれません。信頼を丁寧に積み上げていると、ふとした瞬間に好機が訪れることがあります。
チャンスの神様には前髪しかないと言われますが、日頃から誠実に関係を築いている人ほど、その前髪をしっかりつかめるものです。
焦らず、誠実に、着実に、こうした姿勢を積み重ねることは、組織全体の活動の質を高めるだけでなく、自分の周囲に「相談しやすさ」や「協力を得やすい雰囲気」を育ててくれます。結果として、「自分自身が働きやすい環境」が自然と整い、無用な摩擦やストレスに振り回されることも減っていきます。長く健やかに働き続けるための、最も着実な方法と言えるでしょう。