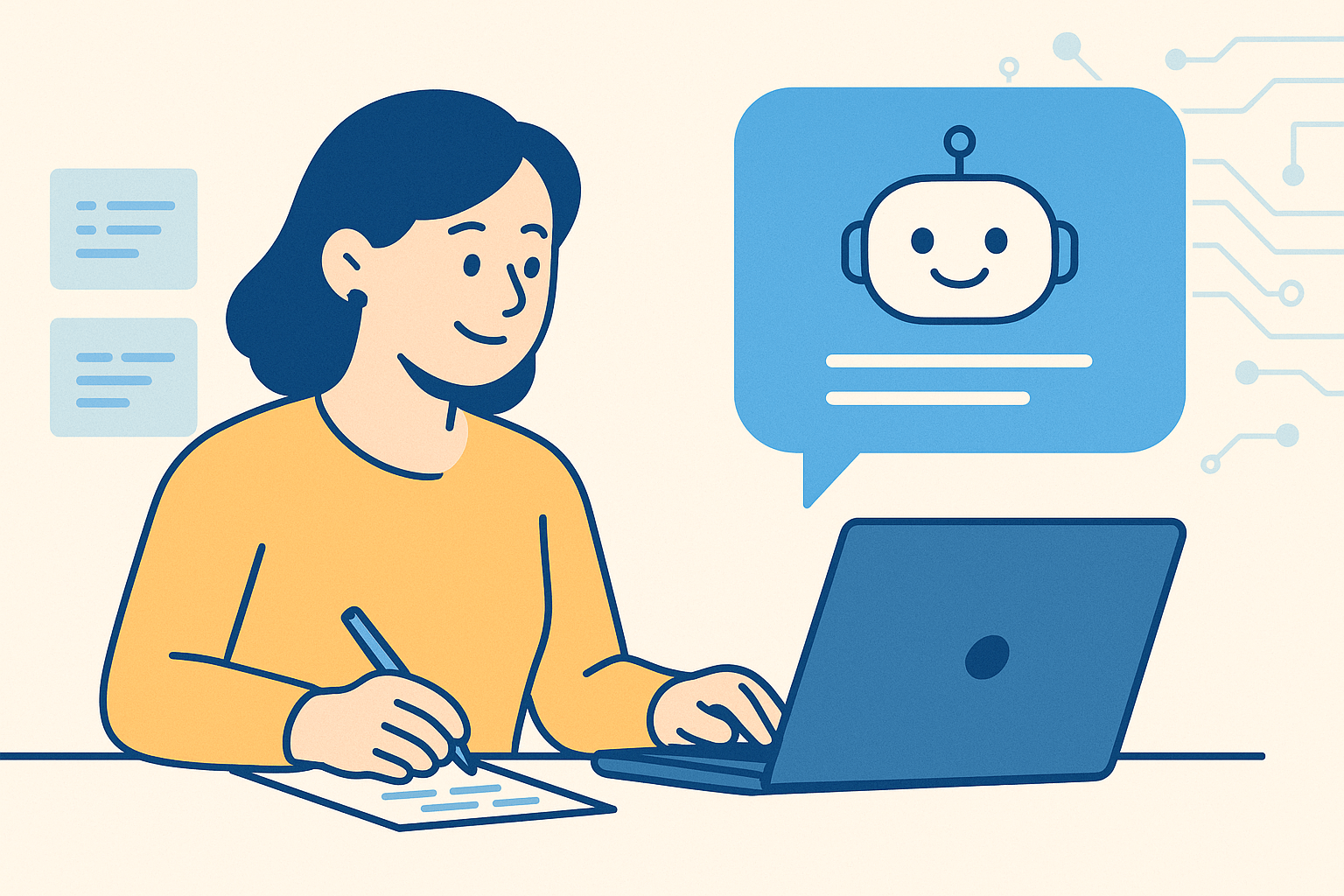
これまで、オンライン研修を制作するための基礎と、具体的な企画・制作プロセスについてお話ししました。今回は、そのプロセスを劇的に効率化するためのツール、生成AI(人工知能)の具体的な活用法に焦点を当てていきます。
「AIって難しそう…」「どう使えばいいか分からない…」と感じるかもしれません。しかし、AIはあなたの強力な「壁打ち相手」であり、最初の「叩き台」を作ってくれる便利なパートナーです。
1. 生成AIの具体的な活用術
私が実際に研修コンテンツの作成で活用している方法を6つご紹介します。
(1) 構成案の叩き台を作る
書籍で得たメモや情報をAIに貼り付け、「これらの内容を使って研修の構成案を作ってほしい」と依頼します。これにより、ゼロから考える手間が省け、作業時間を大幅に短縮できます。
(2) スクリプトの下書きを生成する
構成案に沿って、具体的なナレーション原稿の下書きをAIに作成してもらいます。研修の構成案のほか、スマートフォンの音声入力で思いついた内容、読書メモなどのテキストをAIに渡し、「管理職向け研修動画のナレーション原稿を作成してください。耳で聞いたときに理解しやすい表現にしてください」と指示すれば、思考の整理からコンテンツ作成までが一気に効率化します。
(3) 具体的な説明やワークのアイデアを相談する
「(説明したい内容)を、誰にでもわかるように身近な例で説明して」や、「管理職がチームの心理的安全性を高めるための具体的な行動例を5つ挙げて」といったプロンプトを使って、アイデア出しをしてもらいます。これにより、受講者の理解を深めるための具体的で説得力のある情報を効率よく集めることができます。
アイディアが整理できない時は、AIに話しかけて相談しているうちに、だんだん形になってきます。『ここを足して』『これはカットで』『ここはもう少し具体的に』と指示するだけでOKです。
(4) イラストを効率的に生成する
研修スライドにイラストを入れる際は、まず、作成中のスライドのスクリーンショットを貼り付けて、AIに「このスライドに挿絵を入れたいのですが、どんなものがいいでしょうか。いくつかアイディアを出してください」と、アイディア出しを依頼します。その後、イメージに合ったものを選んで「2番目のアイディアのイラストを生成して」などと指示すると、スライドの内容に合った画像を作りやすくなります。参考にしたい画風や配色があれば、画像をアップロードして「このテイストで作成して」と指示する方法も有効です。
(5) AIへの指示の出し方(プロンプト)を工夫する
AIを使いこなすには、プロンプト(AIへの指示)の出し方が非常に重要です。スクリプトや構成を編集するときには、以下のようなプロンプトを多用しています。
- 「以下の段落の説明では、前後のつながりがイマイチな気がするので、よりスムーズな説明になるよう書き直してください」
- 「以下の段落の『○○』の部分が、少しわかりにくい気がします。もっと簡潔で分かりやすく表現してください」
- 「以下の文章で、内容が重複しているところを整理して、すっきりまとめてください」
- 「以下の文章の『○○』の部分を、もっと具体例を挙げて説明してください」
- 「以下の文章を、スライドに掲載する箇条書きに整理してください」
(6) 音声入力で思考をそのままテキスト化
生成AIを使いこなすコツは、プロンプトに含める情報量や指示の具体性を高めることです。しかし、キーボードで長文を打つのは大変ですよね。そこでおすすめなのが、音声入力の活用です。スマートフォンやパソコンの音声入力を使えば、頭の中で考えたことをそのまま声に出すだけでテキスト化されます。生成AIは、きれいにまとまっていない内容でも、文脈を読み取って要約・整理するのが得意です。この方法を使えば、思考の整理からコンテンツ作成まで、一気に効率が上がります。
AIにお願いするときは、背景の情報を具体的に、たくさん伝えるのがコツです。音声入力なら、思いついたことをしゃべるだけなので、ラクにできます
(7) ChatGPTとGeminiの使い分け(2025年8月時点)
現状の個人的な使い分けとしては、長文の原稿やスクリプトファイルの生成はGoogleのGeminiの方が使いやすいと感じています。一方、スライドのイラスト生成はChatGPTの方が得意だと感じることが多いです。
2. AI活用のリスクと、個性を生む情報取捨選択
AIが作ったものはあくまでも下書きです。ここから人の手で加工や修正を繰り返し、オリジナリティを生み出します。
(1) 情報の正確性に注意する
生成AIは、あたかも正しいかのように誤った情報(ハルシネーション)を生成することがあります。AIが生成した内容を鵜呑みにせず、必ず自分の目で確認することが不可欠です。 特に、専門的な内容を扱う産業保健スタッフの研修では、必ず信頼できる書籍や調査結果で裏付けを取りましょう。最終的な責任は作成者本人にあることを常に意識しておきましょう。
(2) 人間の目と手による編集が「作者」の個性を出す
研修に「どんな内容や情報を盛り込むか」といった、作者の意図や個性が表れる部分は、まだAIに完全に任せられません。AIが作成した内容は一見スムーズですが、作者が伝えたいメッセージが抜け落ちていることもあります。この 「人間の目と手による編集」こそが、研修の質を高め、オリジナリティを生み出すことにつながります。
「この構成はわかりやすいだろうか?」「この説明でちゃんと伝わるだろうか?」と、批判的な視点で確認することも大事です。このようなチェックもAIにお願いできるので、AIの意見も参考にしながら修正していきます。
3. 研修動画の制作形式
研修動画には、解説者が直接話す形式と、コンピューター合成音声を使う形式があります。
- 解説者が話す形式:受講者との親近感や信頼関係を築きやすいという強みがあります。
- 合成音声を用いる形式:収録の手間がなく、常に一定の音質を保てるため効率的です。
それぞれの利点を活かした「ハイブリッド形式」も選択肢の一つです。冒頭の挨拶やまとめといった重要なパートは解説者自身が話し、複雑な解説が続く本編は合成音声を使用することで、効率性と説得力の両方を兼ね備えた研修動画を制作できます。
まとめ
生成AIをうまく活用することで、研修作成における「叩き台作り」を大幅に効率化できます。これにより、これまで時間と手間がかかっていた部分を短縮し、本当に重要な「研修の企画」や「受講者の心に響くメッセージづくり」に、より集中できるようになります。
AIはあくまでツールであり、あなたの専門知識と経験を補完するパートナーです。AIが作成した内容に、あなた自身の「人間の目と手」による編集を加えることで、効率的でありながら、オリジナリティあふれる質の高い研修が完成します。
今回ご紹介した活用術を参考に、ぜひあなただけの最高の研修コンテンツ作りにチャレンジしてみてください。



