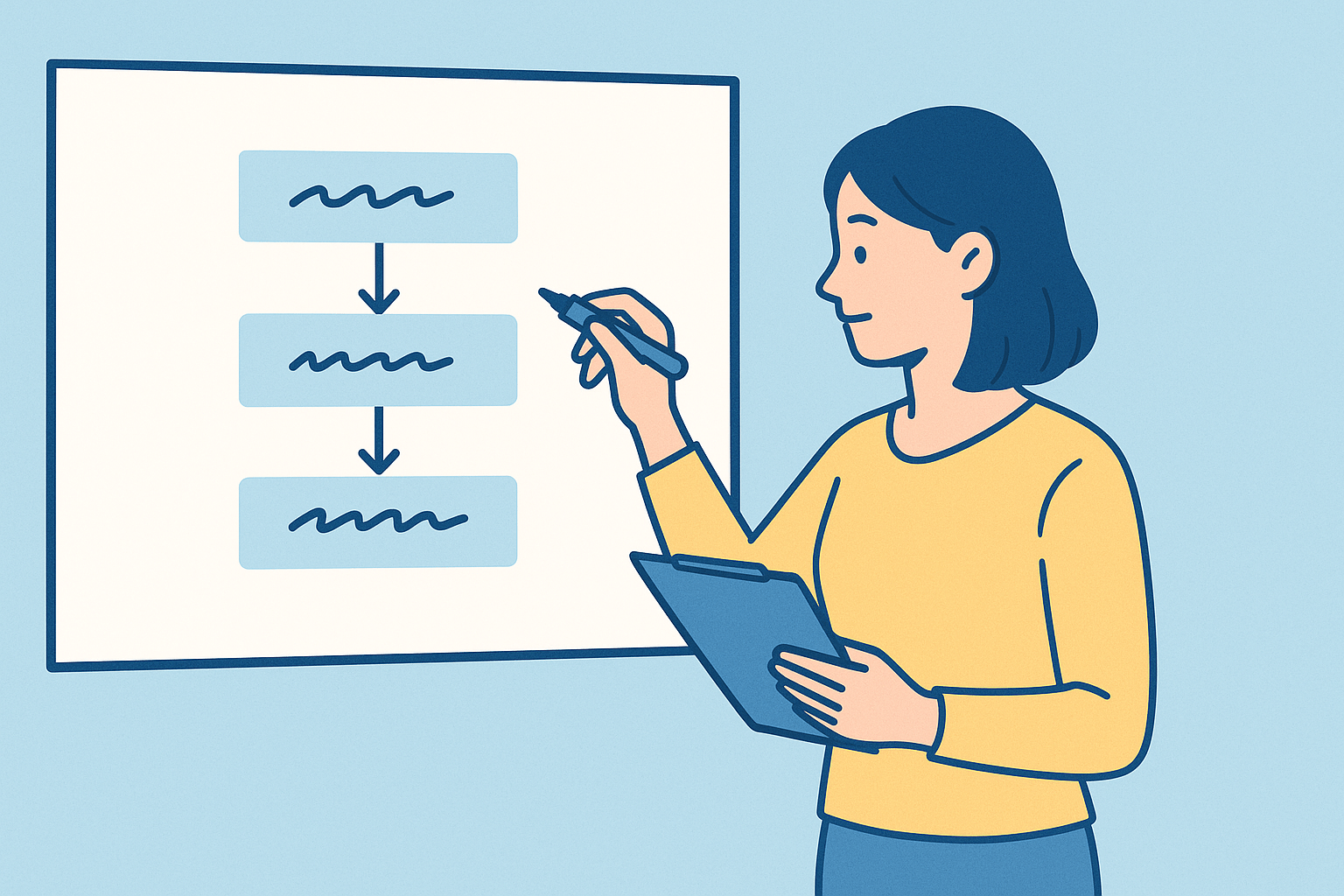
前回の記事では、社内研修を作成する際の基礎的な知識と、受講者の集中力を高めるための基本的な工夫についてお話ししました。今回は、具体的な事例として「心理的安全性」をテーマにした研修を取り上げ、その企画からコンテンツ制作までの流れを、より実践的に解説していきます。
1. 研修のゴールを明確にする
効果的な研修を作る上で最も重要なのは、「学習目標」を明確にすることです。研修を終えた受講者が「何ができるようになっているか」という具体的な行動に焦点を当てた到達点を設定しましょう。
この学習目標は、「~を理解する」ではなく、「行動」で記述することが推奨されます。なぜなら、行動は達成度を客観的に測ることができるからです。
【行動で記述する目標の例】
- 職場の『心理的安全性』の概念を理解し、自分の言葉で説明できる
- 無意識に心理的安全性を損ねてしまう自身の言動を振り返り、リストアップできる
- 心理的安全性を高めるための具体的な行動計画を、明日から実践できる
「理解する」ではなく、「自分の言葉で説明できる」を目標にすると学びが深まります。
隣の人に説明したり、ワークシートに記入したり、自分の言葉でアウトプットするワークを設けると効果的です
2. 効果的な研修コンテンツの作り方
(1) 情報収集は「多読」で深める
研修コンテンツの制作においては、信頼できる情報源から知識を集めることが不可欠です。インターネットの情報だけでなく、関連書籍を複数読む「多読」をおすすめします。同じテーマでも、著者や視点の異なる本を読むことで、理解が深まります。
情報収集は、以下の2段階プロセスで進めると効率的です。
- 通読とメモ: まず本全体をざっと読み、関連しそうな箇所に印をつけて大まかにメモを取ります。
- 構成に沿った整理: 研修の構成案が決まった後、もう一度本を読み返し、各章に必要な情報だけを整理してメモに落とし込んでいきます。この段階では、情報量や説明の順番などはあまり考えずに情報を集めていきます。
(2) 構成の工夫:「チャンク化」と「学習目標」から逆算する
研修動画を作成する際は、まず全体の骨組みである 「構成」 を考えます。人間の短期記憶は一度に扱える情報量に限界があるため、情報を意味のあるまとまり(チャンク)に分割すると理解が深まります。
構成は、「学習目標(到達目標)」から逆算して考えると、必要な情報が整理しやすくなります。今回の研修では、以下のような構成にしました。
- 「心理的安全性」とは何か?: 概念をシンプルに説明し、知識を提供します。
- あなたの行動が心理的安全性を下げているかも?: 受講者自身の行動に目を向けさせ、内省を促します。
- 明日からできる行動計画: 学びを実践につなげ、行動を促します。
研修の構成を考える際、私は3x3x3のフレームワークを意識しています。これは、大きなテーマを3つの主要なパートに分け、さらに各パートを3つのサブポイントに、そして各サブポイントを3つの具体的なメッセージに絞り込むという考え方です。これにより、伝えるべき内容が明確になり、受講者が内容を整理しやすくなります。
研修の構成を考えたり、メモを整理するときに役立つのが「マインドマップ」です。私はXMindといったアプリを使ってマインドマップを作成しています。
(3) 研修を「受け身」にしない「セルフワーク」
動画による研修は、受講者が受け身になりがちです。これを防ぐためには、各パートに短い「セルフワーク」を盛り込むことで、受講者が自ら考え、学びを深める「アクティブ・ラーニング(能動的学習)」を促すことが重要となります。
ただし、こうしたワークは単なる退屈しのぎに終わらないよう、研修の到達目標に沿った内容にすることが肝心です。「正解を当てる」ことではなく、研修で学んだ知識を、自分の経験や職場での状況と結びつけて考えてもらうことで、理解はより深まります。例えば、例となる事例を提示して、学んだ内容をその状況にあてはめて考えてもらうような「実用的なワーク」にすると効果的です。こうした工夫によって、受講者は学んだ内容を実際の行動に移しやすくなります。
まとめ
研修の成功は、単に情報を伝えるだけでなく、受講者が主体的に学び、行動に移せるような設計にかかっています。この記事でご紹介したステップは、どのようなテーマの研修にも応用可能です。次回の記事では、この研修コンテンツの作成をさらに効率化するための「生成AIの具体的な活用術」について、詳しく解説していきます。



